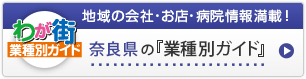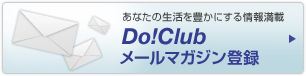王寺町特集
[奈良県]
明治22年に町村制が実施され、当時の藤井村と合併、そして現在の礎となる「王寺村」が生まれました。
この王寺村の大きな発展を支えたのは、明治時代の湊町から奈良の間をはじめとする様々な鉄道の開通です。農村としての色合いが濃かった王寺ですが、鉄道利用で豊かな物資が届くようになり、商業も盛んになってきました。
こうして村勢が飛躍的に進展し、大正15年2月11日に町制が施行され、「王寺町」が新しく誕生しました。
昭和32年には、香芝町の大字畠田を編入し、商都大阪の衛星都市として発展してきました。
王寺町のいいトコ!!
王寺町で憩い・楽しむ
菩提キャンプ場&冒険の森inおうじ(ぼだいきゃんぷじょう&ぼうけんのもりinおうじ)
BBQ場やキャンプ場を併設した複合型施設で1日中楽しめます。高さ10メートル越えの木の上で行うツリートップアドベンチャーは、子どもから大人までスリルたっぷり。最後の池越え150メートル超のジップラインは圧巻です。

畠田公園(はたけだこうえん)
菩提キャンプ場の上にある見晴らしの良い公園です。周囲は木々が豊富で、季節ごとの自然を感じることができます。
ふわふわドームや健康遊具などを設置しているので、体を使った外あそびが存分に楽しめます。他にも砂場や小さな滑り台もあり、夏でも木陰がたくさんあるので、小さなお子さんのお出かけにも最適です。
公園から続く階段を歩くと菩提キャンプ場まで行けますよ。

大和川ふれあい広場(やまとがわふれあいひろば)
一寸法師のお椀などの遊具や芝生広場に憩い、菜の花や水仙、彼岸花も四季の彩りを添えて、人々をなごませています。
また、王寺町及び三郷町の高水敷等を利用した、一周約4キロメートルのジョギングコースを整備しています。

舟戸児童公園(ふなとじどうこうえん)
奈良県初の駅の1つである王寺駅を中心に、鉄道のまちとして栄えた王寺を象徴するものとして、D51形蒸気機関車895号機(王寺町指定文化財)が静態保存されています。
日没から23時まではイルミネーションで飾られます。

王寺町の名所・文化
達磨寺(だるまじ)
『日本書紀』によると、推古天皇21年(613)12月、聖徳太子が道のほとりに臥せっていた飢人を見つけ、飲み物と食べ物、それに衣服を与えて助けましたが、飢人は亡くなりました。そのことを大いに悲しんだ聖徳太子は、飢人の墓をつくり、厚く葬りましたが、数日後に墓を確認してみると、埋葬したはずの飢人の遺体が消えてなくなっていました。
この飢人が、のちに達磨大師の化身と考えられるようになり、達磨寺は生まれました。
達磨寺内には、二人の出会いを描いた屏風絵《片岡山のほとり》(橋本関雪作)の複製品を公開しています。

乳垂地蔵(ままたれじぞう)
わが子の乳母のお乳が少ないことを案じた推古天皇が、この地蔵に祈願したところ、たちまちに乳母のお乳が出るようになったといわれます。他に、中世の石造物などもあります。

火幡神社(ほばたじんじゃ)
今の王寺町には、たくさんの新しい住宅地ができています。しかし、町内の神社には、まだまだ古い習わしが残っています。
子どもが生まれると、神社の氏子(うじこ)になったしるしに、その年の秋祭りに絵馬を奉納します。
絵馬の絵柄は、男の子なら宇治川先陣、女の子なら尉(じょう)と姥(うば)が多いようです。
絵馬はさまざまな願いを込めて奉納されるもの。この習わしは、今でもつづけられているので、町内の神社の拝殿や絵馬殿には、こうした絵馬が所せましと飾られています。

畠田古墳(はたけだこふん)
直径が約15メートルの円墳で、奈良県指定史跡です。横穴式石室の左右には石を貼り付け、背後には溝がめぐらされています。発掘調査では、銅芯金張りの耳環が良好な状態で出土しました。

片岡神社(かたおかじんじゃ)
『延喜式』の神名帳に記される「片岡坐神社」に比定されています。八幡大神、住吉大神、豊受大神、清滝大神、天照大神の五柱をお祀りし、現在は王寺全体の鎮守となっています。