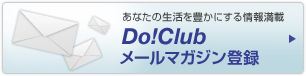輪之内町特集
[岐阜県]
私達の住んでいる輪之内町は大昔、伊勢湾とつながる海であったと言われています。その後、伊勢湾が陸地になったり、海に沈んだりしながら、長良川をはじめ、多くの川が上流から土砂を運び、現在の濃尾平野をつくってきました。
その頃の川は自然の流れにまかされており、川はたえず場所を変えて、氾濫をくり返し、生命、家屋、農地等を奪いました。
明治30年に、福束新田・中郷新田・藻池新田・海松新田・下大榑新田・下大榑村・大吉新田・海松村・柿内村を以って仁木村を、本戸村・中郷村・里村・南波村・福束村・塩喰村を以って福束村を、五反郷村、五反郷新田、上大榑村、上大榑新田、楡俣村、楡俣新田、大藪村を以って御寿村となり、明治35年御寿村は町制をしいて大藪町となりました。
昭和29年町村合併促進法により、仁木村・福束村・大藪町が合併し現在の輪之内町が発足しました。
輪之内町のいいトコ!!
輪之内町で憩い・楽しむ
輪之内ふれあいフェスタ
西濃地方の秋のまつりとして定着した「輪之内ふれあいフェスタ」。バザーや芸能人によるステージ、ビンゴ大会など楽しめる企画がいっぱいです。

輪中堤の桜
水害から地域を守った輪中堤を後世に引き継ごうと植えられた600本近い桜が、桜のトンネルとして人々の目を楽しませてくれます。

あじさいロード
本戸輪中堤周辺のあじさいロードには約6,000株ものあじさいがあり、隠れたあじさいの名所となっています。6月中旬が見頃です。

輪之内町の名所・文化
水神神社
宝暦5年(1755年)に薩摩藩のお手伝普請による「薩摩堰」が完成しましたが、その後の出水で機能が低下しました。そこで洗堰組合が宝暦8年(1758年)、その上流に「大榑川洗堰」を構築。江戸末期に画かれた大榑川洗堰の鳥瞰図には、二番猿尾の頂上部に祠が画かれ、この祠が水神神社になります。昭和初期に現在地に社殿を新築し遷宮祭を斉行しました。
| 所在地 | 輪之内町大藪 |
|---|

枡屋(ますや)伊兵衛(いへい)の墓
伊兵衛は、宝暦治水工事の際、人柱になった人物。江戸神田紺屋町に住み、出身地は多良(現・大垣市上石津町)でした。三之手工事の責任者になった水行奉行高木内膳に同行。凄惨なまでの難工事を見て「これは水神の怒りによるものだ。人柱となって怒りを静めよう」と濁流に身を投じました。
洗堰は、宝暦治水の際、長良川と大榑川の分岐点に造られました。
| 所在地 | 輪之内町大藪1865(円楽寺境内) |
|---|

関ケ原合戦戦没者埋葬の北塚(きたづか)
東大藪の北部の水田の中に一畝ほど小高く土を盛りあげた塚があります。これが北塚です。慶長5年(西暦1600年)の9月15日の関ケ原合戦のおよそ1ヵ月前に行われた「福束(城)の戦い」で戦死した東・西両軍の死者をあわれんで土地の人たちがここに埋葬して成仏を祈った塚だということです。
| 所在地 | 輪之内町大藪 |
|---|

輪之内町の特産・名物
徳川将軍家御膳米
ほかのお米に比べて粒が大きいハツシモという種類の中でも、こだわりの栽培方法で作られた輪之内町産のブランド米です。
輪之内町では江戸時代初期から幕府直轄領として将軍家台所のお米を産出してきました。米の品質や管理の良さが評価された歴史があったことから『徳川将軍家御膳米』と名付けられました。もっちりとした食感と冷めてもおいしいのが特徴です。

懸崖(けんがい)菊
鉢植えした菊を、横に出した長さ約65センチメートル程の針金に這わせて形にします。直径約3センチメートルの小菊の花が一面に咲き誇り、この鉢に垂れ下がった形から「懸崖菊」と名付けられました。
町のけんがい菊生産組合では、昭和30年代から「けんがい菊」作りを始め、今では町の特産品になっており、5号鉢と6号鉢の生産量は日本一を誇るまでになっています。色は赤色と黄色が主流で、およそ70パーセントを関西市場へ、30パーセントを中部・関東市場へ出荷しています。

ミニバラ
背丈が25から30センチメートルで、一鉢に約15輪の花をつけます。色は、あざやかなシルクレッドが主流となっています。平成3年頃から作り始め、東海・北陸・関東方面へ出荷しています。手入れが簡単なことから幅広い層に人気があります。