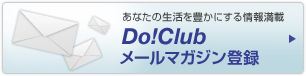御嵩町特集
[岐阜県]
昭和30年2月に御嵩町・中町・伏見町・上之郷村が合併し御嵩町は誕生しました。
2025年2月、御嵩町は誕生から70周年を迎えます。
御嵩町のいいトコ!!
御嵩町で憩い・楽しむ
中山道
江戸時代、江戸と京都のあいだを結んだ中山道は、人や物、情報や文化の往来する主要な街道として栄えました。
現在の御嵩町域には、かつての中山道の風情が色濃く残されており、このうちおよそ3.6キロメートルが国の史跡に指定されています。途中、「牛の鼻欠け坂」「謡坂石畳」「御殿場」など、みどころも点在する歴史街道です。

商家竹屋
明治10年(1877)頃建築の商家竹屋は、江戸期に本陣・野呂家より分家し、豪商として栄えました。
明治期の建築ではあるものの、御嶽宿が栄えた江戸期の風情を感じさせる御嶽宿内でも貴重な建築物といえます。主屋および茶室が町指定文化財となっています。

中山道「伏見宿」
元禄7年(1694)に誕生した、比較的新しい宿場町。木曽川の水運を利用した新村湊から多くの物資が運び出され、賑わいを見せていました。現在、街道は国道となっていますが、周辺には古い建築物や古墳など多くの史跡が残っています。

御嵩町の名所・文化
大智山愚溪禅寺
室町時代の応永年間(1394~1428)に開創された愚溪寺は、臨済宗妙心寺派の高僧・義天玄承が師の跡をたどって、鈴が洞の山中に「愚溪庵」を開いたのがはじまりとされています。

多宝塔
愚溪寺境内に併設された「多宝塔」は、江戸時代末期に愚溪寺が北西の山中から移転してきた際の記念として、万延元年(1860)に美濃出身の野村作十郎が手がけたもので、二重の塔とも呼ばれています。

御嵩薬師祭礼(岐阜県重要無形民俗文化財)
地域の民衆の生活のなかから生まれ、1000年以上にわたり受け継がれてきた伝統ある祭礼行事で、「天下泰平」「五穀豊穣」を祈る大祭です。「蝿追」と「獅子」による舞いはこの祭りのハイライトともいえ、樒の枝で参拝者の頭を叩いてまわることで、厄除けができるとされるとてもユニークな舞いです。

御嵩町の特産・名物
みたけからあげ

笹クッキー

手づくりの木のもの

志野湯呑