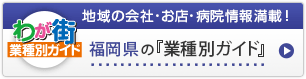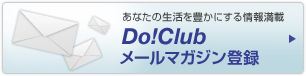小竹町特集
[福岡県]
明治17年、勝野・新多・新山崎・南良津・御徳・赤地・中泉の7ヶ村で勝野村外6ヶ村戸長役場を置き、明治22年町村施行の際に中泉村は福地村(現直方市)に併合され、他の6ヶ村を合併して勝野村として発足しました。昭和3年(1928)1月1日、勝野村に町制が施行され現町名に名称変更されました。町名の由来は古来町内の街道沿いに竹薮が生い茂り、小竹の町まで続いていて、「小竹の処」といわれたのが町名のおこりになったといわれています。
小竹町のいいトコ!!
小竹町で憩い・楽しむ
小竹町遠賀川 河川公園
旧庁舎前からふれあい橋へ向かって広がる道と1本の樹木があり、開放的な空間です。春には菜の花が一面に咲き、夏には“ひがん花まつり“の催しがあるなど、町民のやすらぎの場として親しまれています。

遠賀川自然公園“わくわくごとくリバー”
国土交通省九州地方整備局遠賀川河川事務所と連携し、生き物が遠賀川から田んぼへ行き来できるように水路等を整備した体験型施設です。平成28年3月に完成し、北小学校の児童が命名しました。
公園には魚類・植物・鳥などが生息しています。川に住む魚たちをはじめ、カエルや貝、トンボなどさまざまな生き物たちのすみかや産卵場所をつくることですみやすい環境になっています。

昭和の森
自然とふれあいながら健康増進を図るためにつくられた公園です。月1回ペースで“こたけプレーパーク”が開催され、子どもたちがロープのアスレチックや秘密基地などをつくったりして自然遊びを楽しんでいます。

山の里自然農園
炭鉱で栄えた筑豊地区を象徴する“ボタ山”の跡地で高台にあり、筑豊が一望できる広大な農園です。園内は、約1700本のブルーベリーの木が植えられ、オリーブも栽培されています。ブルーベリー園が開園する夏には、多くの人たちがブルーベリー狩りや手作りピザ体験などを楽しみます。

小竹町の名所・文化
合屋古墳(ごうやこふん)
6世紀後半に築造された円墳横穴式石室は前後2室からなる複重構造です。小竹町内に現存する唯一の石室古墳であり、当地域の大変貴重な歴史資料として保存されています。

絹干神社(きぬぼしじんじゃ)
毎年田植えが終わると五穀豊穣、家内安全を祈って神相撲が行われていました。境内には自然林があって、特にコバンモチの巨樹は、県下でも珍しく貴重なものです。
堀河天皇が寛治2年(1088年)新多区の上日鼻に歓請され、至徳元年(1384年)社地を同区一井ケ浦に遷宮。祭神は、機織姫命、同区の氏神様として信仰を集めています。大正9年(1920年)神殿と拝殿が改築されました。

六地蔵(ろくじぞう)
小竹上町にあるニ体型六体組の六地蔵は寺記によれば寛延3年(1750年)に、川上からこの地に流れ着き、「河中に尊い仏像がある。早く引き上げよ。」とお告げがあり、引き上げられたと言い伝えがあります。
六つの地蔵は人間の六道(地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上)の罪苦を救うといわれています。

小竹祇園山笠
五色の幕やちょうちん、飾りをほどこした山笠は、疫病退散や怨霊沈静を願う、小竹貴船神社に伝わる奉納行事です。約200年以上にわたり伝承し、地域で守り続けています。
和太鼓の音とともに駆け巡る山笠は、高さ約4メートル、幅約2メートルあります。大きく上下に揺らす“がぶり”や、車輪を軸に回転させる“引廻し”が見せ場です。

南良津獅子舞
宝暦2年(1752年)に8年続いた豊作を祝って獅子舞を「秋のおくんち」に奉納したのがはじまりとされています。毎年稲刈りが終わる10月の時期に、家内安全・五穀豊穣などの願いを込めて受け継がれてきた南良津区に伝わる獅子舞。前楽・古楽・道楽・出端の型があり、雄獅子と雌獅子が笛や太鼓のリズムに合わせて勇壮活発に舞を繰り広げます。